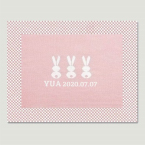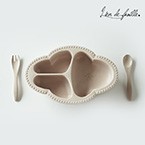よくわかる!1歳までのイベントスケジュール
公開日: 2019年11月05日 / 最終更新日: 2024年11月27日

赤ちゃんの成長をお祝いするイベントは出産後1歳までに集中しています。
初めての育児に追われながら、産後にお祝いイベントの準備をするのは大変です。
赤ちゃんが生まれる前にどんなお祝いやイベントがあるのか知っておくと、素敵な思い出をしっかり残せるのではないでしょうか。
今回は1歳までのイベントスケジュールをまとめますので、赤ちゃんのすこやかな成長を楽しみにしつつ、参考にしてしっかりと準備をしていきましょうね。
目次
産後慌てないために知っておこう!1歳までのお祝いやイベントがたくさん!

赤ちゃんの成長を祝う様々なイベント。
なんとなく知っている方もいれば、どんなお祝いをすればいいのかまったくわからないという方もいると思います。
産後、ママの体調が不安定な中、赤ちゃんのお世話をしながらイベントやお祝いの準備をするのはかなり大変です。
というのも、1歳を迎えるまでにはたくさんのお祝いがあるからです。
特に産後半年までは、短い期間に様々なお祝いイベントが!
赤ちゃんのお世話に加えて欠かせない予防接種や乳児検診もあるため、早めに知っておくとスケジュールも立てやすいのではないでしょうか。
どんな行事があるのか、順番にご紹介します。
御七夜(おしちや)
御七夜は、赤ちゃんが生まれてから7日目の夜にするお祝いです。
生まれた当日が1日目なので誕生日の6日後になります。
生まれた次の日を1日目とする場合もあります。
平安時代に始まったとされるこのお祝いは、赤ちゃんの健やかな成長を願う最初のイベント。
栄養状態が良くなかった古い時代には生後すぐに命を落とす赤ちゃんも多かったため、節目となる7日目に成長を祈願したそうですよ。
御七夜で命名式を行い、祝い膳を食べるのが一般的です。
命名式では、それまでに考えていた赤ちゃんの名前を命名書に書いて披露します。
お祝いに集まった家族や親戚に赤ちゃんを家族の一員として紹介するんですよ。
神棚や床の間に命名書を飾って、神様に赤ちゃん誕生を報告するのが習わしでしたが、現代では簡単に壁などに飾るお家も増えています。
記念に赤ちゃんの手形や足形をとったり、記念撮影する人も多いですね。
命名書は奉書紙と言われる特別な和紙を使うのが正式なやり方ですが、半紙や色紙などを使った簡略化した方法が一般的になってきました。
命名書はお宮参りまでの約1ヶ月間飾っておくのが習わしでしたが、お宮参り後も記念に飾っておく人もいます。
命名式の後には家族や親戚で祝い膳をいただきます。
祝い膳には赤飯と鯛の尾頭付きを用意するのが定番。
ほかにはお造りや天ぷら、はまぐりのお吸い物などが一般的です。
多くの産院では出産後1週間程度で退院するため、産院でお祝い膳が出てくることも多いんですよ。
■赤ちゃんと会えた喜びや、誕生への感謝の気持ちを込めた記念品
記念日のおすすめ
お宮参り(おみやまいり)
お宮参りとは、産土神様(うぶすながみさま)に無事に生まれた報告する行事です。
健やかな成長を願ってお参りをしたり、ご祈祷をします。
産土神様は赤ちゃんが生まれた土地に宿る神様ですが、他の御縁のある神社にお参りしても構いません。
安産祈願で訪れた神社に、産後にお参りする方もいます。
お宮参りは男の子の場合生後31日頃、女の子の場合生後32日頃という決まりがありますが、ママや赤ちゃんの体調や天候を考慮し、日程をずらしてもOKです。
地域によっては生後100日にお参りをしたり、縁起の良い大安・先勝・友引を考慮して日程を決める場合も。
赤ちゃんにとっては初めての外出となる場合も多いため、真夏や真冬など、赤ちゃんの負担にならないよう柔軟に決めましょう。
ママにとっても、産後のお出かけは負担になるので、無理はしないでくださいいね。
一般的には父方の祖父母がお宮参りに付き添うのが習わしですが、最近では母方の祖父母が付き添うことも多くなってきました。
また、両方の祖父母が揃ってみんなでお参りする人も増えています。
お参りのあとに記念撮影をしたり、会食に行くという人も。
赤ちゃんには宮参り着と言われるお祝い着やベビードレスを着せます。
白羽二重と呼ばれる内着の上に祝着(のしめ)を羽織るのがお宮参りでの赤ちゃんの正装なんですよ。
男の子の場合には、袖の下と腰まわりに兜や鷹、武者、龍などの勇ましい柄が描かれたものが人気で、色は黒や紺、緑などが定番です。
女の子の場合には桜や牡丹、蝶、毬などが描かれた華やかなものが定番で、色は赤やピンクが一般的です。
最近では淡いブルーなども人気なんだそうですよ。
お祝い着は赤ちゃんに被せるような形で、抱っこする人の方にひっかけて結びます。
お宮参りのしきたりでは、赤ちゃんを抱くのはママではなく父方の祖母の役目とされてきました。
昔は出産は穢れ(けがれ)とされていたためです。
しかし現在のお宮参りでは、昔のような決まりはありません。
家族で相談して決めるのがいいでしょう。
赤ちゃんに祝着を着せる場合、家族も合わせて着物を着るのが望ましいとされています。
ママと祖母は訪問着や色無地などを着るとよりお祝い感も出ますね。
赤ちゃんにベビードレスを着せる場合には合わせてセレモニースーツやフォーマルなワンピースにしましょう。
パパはスーツを着るのが一般的です。
赤ちゃんが祝着の場合には礼服、ベビードレスの場合はダークカラーのスーツを着ます。
このように決まりはありますが、絶対にこれを着なければならないということはありません。
実際には赤ちゃんに祝着を着せてママはセレモニースーツという人も多いんです。
産後の体調不良の中、着慣れない着物でお参りするのは大変ですから。
大事なのは赤ちゃんを引き立てる、控えめできちんとした服装です。
カジュアル過ぎたり派手過ぎる服装を避け、家族全体のバランスを考えるのがマナーですよ。
■お宮参りにおすすめのアイテム
お宮参りのおすすめ
食い初め(おくいぞめ)
離乳食がスタートする生後100日頃に行うのがお食い初めと言われるお祝いイベントです。
この先、赤ちゃんが食べ物に困らないようにと願いを込めて行います。
お食い初めも平安時代から行われている伝統的なお祝いです。
100日祝い、ももか祝いとも呼ばれています。
お食い初めでは祝膳を用意し、赤ちゃんに食べさせる真似をするのが習わしで、メニューの定番は赤飯、鯛の尾頭付き魚、お吸い物、煮物、香の物。
お料理に加え、歯固め石を添えることもあります。
歯固め石は氏神の境内から授かったり、近所で拾ってきたりと手に入れる方法は様々。
赤ちゃんの口に触れるものなので、しっかり洗浄し衛生面には気を使いましょう。
祝膳は脚付きのもので、食器は漆塗りのものを使用するのが基本です。
男の子は内側も外側も朱塗りのもの、女の子は内側が朱色で外側が黒色のものを使用するのが習わしです。
祝膳を一から揃えて準備するのが大変!という人のために、「お食い初めセット」として通販サイトなどでも購入することができます。
中には食器がセットになっているものもあり、お食い初めの儀式後も普段遣いできる便利なものも!
お食い初めで行うのは歯固めの儀式です。
用意した祝膳のお料理を赤ちゃんの口に軽く当てて食べさせるマネをし、丈夫な歯が生えるようにと願います。
生後100日頃の赤ちゃんのお口にはまだ歯が生えていません。
あえてこの時期にお祝いをすることで「丈夫な歯を生やし、一生食べるものに困らないように」との願いを込めるのです。
現代の日本では食べ物に困るというのは考えにくいことですが、昔は経済事情や食糧事情で子供にでお腹いっぱい食べさせてあげられない時代もありました。
昔から変わらず、健やかに育ってほしいという親の願いが伝わってくる風習だと思いませんか?
食べさせる真似をする人も、できるだけ年長の同性の人がいいとされています。
赤ちゃんの長寿を願ってのことなんだとか。
イベントに込められた願いを知ると、より大事に行いたくなりますね。
■ながく使えるおすすめのベビー食器
ながく使える膳・椀・箸のセットがおすすめ。また離乳食づくりに便利なブレンダーもおすすめです。
お食い初めのおすすめ
ハーフバースデー
生後6ヶ月を記念して行うのがハーフバースデーというイベントです。
日本の伝統的なお祝いではなく、海外から持ち込まれたお祝いです。
そのため、決まった形式はありません。
より自由度の高いイベントと言えるでしょう。
記念に写真館で写真を撮る人が多いようです。
離乳食が始まっている赤ちゃんには、ケーキに見立てた離乳食を作る先輩ママも!
生後6ヶ月頃になると、ママも赤ちゃんとの生活に慣れてきます。
産後の体調不良も落ち着いてくる頃です。
これまでの成長を振り返り、ひとつの節目として自分なりの工夫で素敵な記念日にしてみてくださいね。
■ハーフバースデーにおすすめのアイテム
生まれた時から心も体も大きく成長した赤ちゃん。これから使える知育玩具やベビー服でお祝いしましょう。
ハーフバースデーのおすすめ
初誕生日
いよいよ1歳。
ママにとっても産後1年を迎える節目のお祝いイベントですね。
多くの赤ちゃんが離乳食も後期まで進んでいる時期のため、赤ちゃん用のケーキやごちそうなどを用意し、盛大にお祝いしましょう。
無病息災を願う初誕生には「一升餅」や「選び取り」というお祝いが一般的です。
「一升餅」は一升(約2kg)のお餅を赤ちゃんに背負わせるお祝いです。
背負わせるのではなく踏ませたり、赤ちゃんをわざと転ばせたりと地域によって様々です。
一生食べ物に困らないように、円満に生きられるように、地に足をついていられるようにと、赤ちゃんへの願いが込められてます。
「選び取り」は赤ちゃんが将来、何の職業に就くか、どんなふうに育つのかを占うものです。
赤ちゃんの前に様々な道具を置き、最初にどれを手に取るか、興味を示すかで将来就くであろう職業や人となりを当てるというイベントです。
たとえば電卓やそろばんを触ったら「商売人になる」、本を触ったら「学者になる」、お金を触ったら「お金持ちになる」、定規を触ったら「しっかり者になる」といった具合いです。
地域ごとに用意する道具や解釈も違うそうですよ。
■1歳のお誕生日におすすめのアイテム
生まれた時から心も体も大きく成長した赤ちゃん。これから使える知育玩具やベビー服でお祝いしましょう。
1歳の誕生日のおすすめ
慌てないために知っておこう!年中行事や月齢フォトも大事なお祝いイベント!

ご紹介した1歳までの節目のお祝いイベントの他にも、年中行事や月齢フォトを撮ることも大切な記念になります。
初節句
3月3日の桃の節句(ひな祭り)は女の子、5月5日の端午の節句は男の子の節目のお祝いになります。
ひな祭りには雛人形を飾り、端午の節句には鯉のぼりや五月人形を飾ります。
初節句を迎えるときに1,2ヶ月に満たないという赤ちゃんは、翌年に初節句のお祝いを行うという方も多いです。
産後の体調の回復や他の行事との兼ね合いもあるため、無理せず余裕を持ってお祝いするのがいいでしょう。
桃の節句も端午の節句もポピュラーなイベントですが、初めての節句は特別なもの。
特別なお祝いになるでしょう。
■初節句におすすめのアイテム
初節句のおすすめ
初正月
初めて迎えるお正月も赤ちゃんにとっては大事なものです。
お正月は普段忙しくて会えない親戚が集まり、赤ちゃんとの対面を果たすことができますね。
遠方に住む親戚や従兄弟との出会いも大切な思い出になります。
また、生まれてから初めてのお正月には、赤ちゃんの写真や家族写真を載せた年賀状を出しましょう。
産後はお出かけも難しくなり、遠方でなかなか会うことができない親戚や友人にも赤ちゃんを紹介するいい機会になります。
月齢/記念フォト
赤ちゃんが生まれると、可愛さのあまり写真を撮りまくって、気がついたらスマホの容量が減っていたということも。
我が子の可愛さをしっかり記録に残しておきたいのは親心ですよね。
そこで外せないのは月齢フォトです。
月齢フォトは、赤ちゃんの成長記録として毎月撮るもので今人気が集まっています。
写真館やスタジオに行かなくても、自宅で、あるものを使って撮るのが特徴です。
月齢の数字と一緒に映すことで生後何ヶ月なのかを表します。
オムツを並べて表現したり、ステッカーやシールを使うママが多いんですよ。
また、毎月同じものと並べて写真を撮っておくと、成長の過程がよくわかります。
代表的なものはぬいぐるみですね。
節目ではなくとも、初めての寝返りや初めての離乳食も大事な記念フォトですね。
産後のママは、なかなかお出かけできないこともしばしば。
家の中でも赤ちゃんと一緒に毎月写真を撮って楽しむ人もいますよ。
赤ちゃんの写真をたくさん撮っておけば、見返したときに話に花が咲くでしょう。
■月齢フォト・記念日フォトにおすすめのアイテム
お祝いを盛り上げてくれるタペストリーや記念日が分かりやすい数字のつみき、赤ちゃんと大きさ比較ができるぬいぐるみなどのアイテムと一緒に写真を撮るのがおすすめです。ジェリーキャットやミッフィーのぬいぐるみはファーストトイにも大人気!
記念日フォトにおすすめ
まとめ

赤ちゃんの成長をお祝いするイベントをご紹介しました。
1歳までにこんなにたくさんお祝いイベントがあることをご存知でしたか?
古くから行われる行事には、赤ちゃんの健やかな成長を願う気持ちが込められています。
絶対にすべてのお祝いをしなければいけないというわけではありません。
赤ちゃんや産後ママの体調、乳児検診や予防接種の日程を考慮しながら無理のない範囲でお祝いしてあげてくださいね!
産後のママの負担が減るように、最近はお祝いグッズやサービスも増えています。
うまく活用し、お祝いイベントを楽しみましょう。
関連記事はこちら
-

(2023年)ママが本気で嬉しかった!出産祝いランキング♪
「出産祝いって何を贈ったらいいの?」いざ探すと、たくさんの商品があって迷ってしまうものですよね。
-

出産後のお見舞いのNGポイント
出産後のお見舞いは、赤ちゃんとママに配慮してこそ喜ばれるものです。お見舞いに行く時は、必ずママの体調を伺い、お見舞いに行って差し支えない状態かどうか確認してから伺うようにしましょう。
-

出産祝いで喜ばれる人気タオルギフト
出産祝いで喜ばれるギフトのひとつに、タオルギフトがあります。赤ちゃんが生まれるとタオルを予想以上に使いますし、家族が増えるので気付くとタオルが足りなくなっていることがあります。
-

出産祝いで贈りたい名入れギフト
名入れギフトとは、赤ちゃんの名前を入れたギフトのこと。名前を入れることで特別感を出すことができ、贈った相手にお祝いする気持ちが伝わる効果があります。注意すべき点をおさえつつ、ぴったりのギフトを見つけましょう。